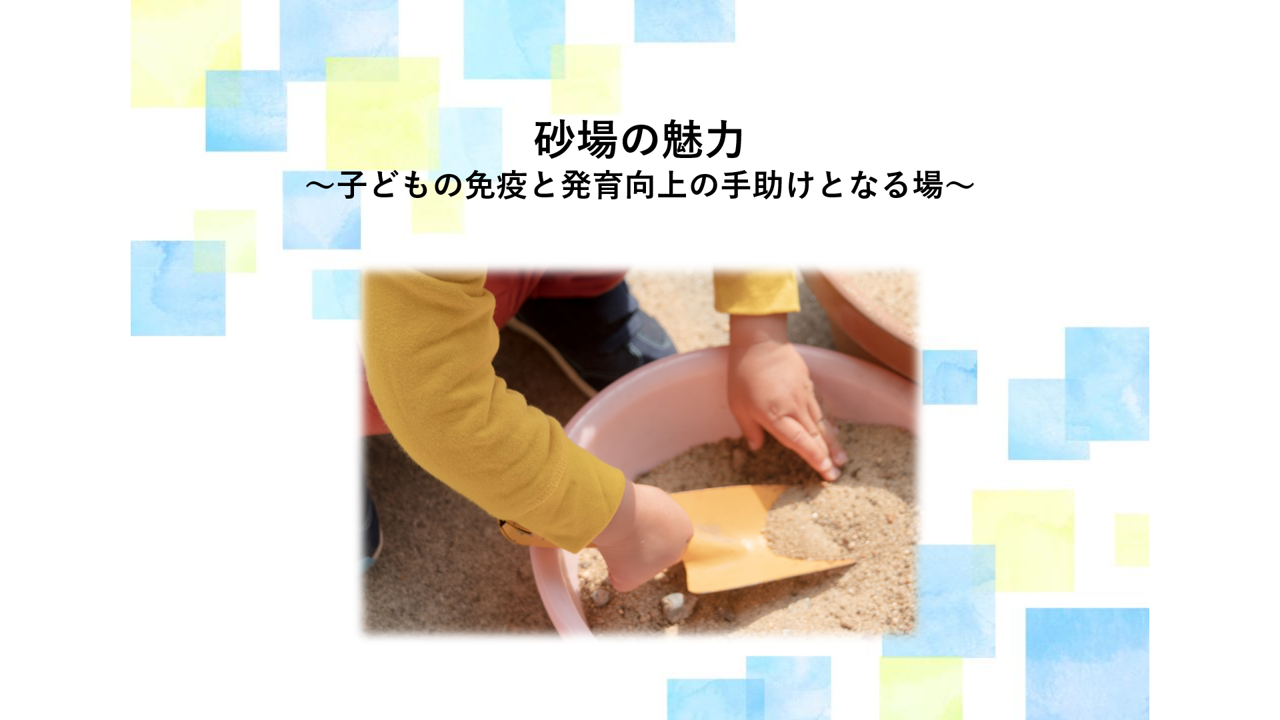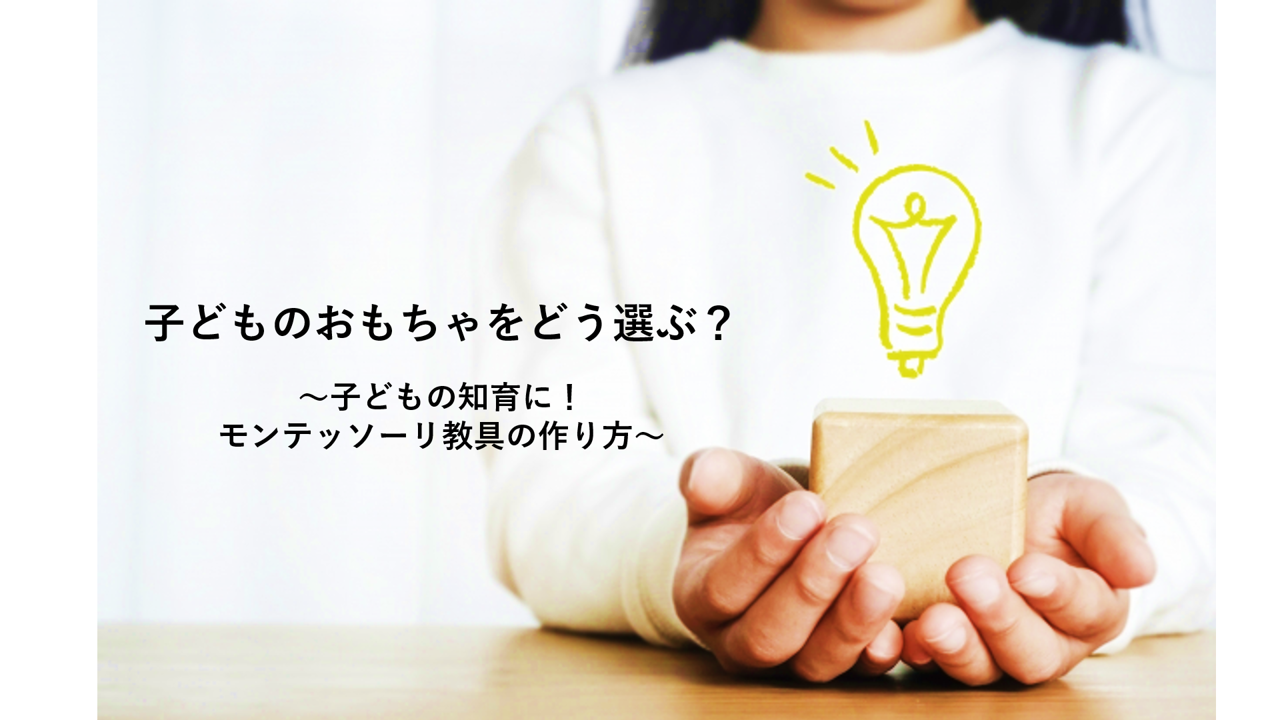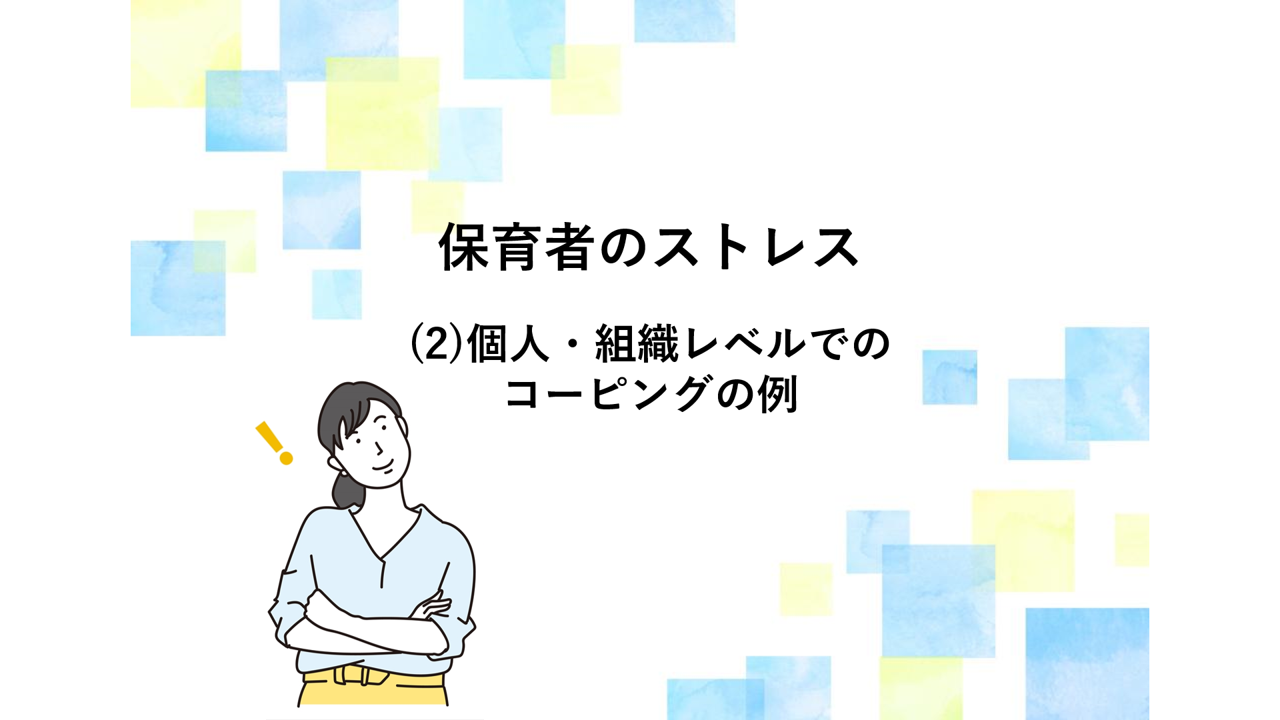▼年齢別の週案記入例は下記記事にてご紹介!
子どもの姿
- ひな祭り制作では、使用したい柄が他児と同じになってしまった際に全体で話し合いをしたところ、折り紙を子どもたち同士で譲り合う姿があった。
- 戸外遊びでは小集団遊び(鬼ごっこ)のルールを自分たちで確認し合い、楽しんでいた。
- 似顔絵を描く際、顔のパーツ、位置、色などを自分たちで考えながら描くことが出来ていた。
- 戸外ではサッカーボールを蹴ってパスし合ったり、フラフープを使って電車ごっこ、フープ渡しゲームをするなど他児と一緒に遊ぶことが出来る遊びを楽しむ姿が見られた。
- 生活リズムは少しずつ戻ってきているものの、体力が落ちている子が多く給食の時間に疲れてしまい、食事が進まない日が続いた。
- 保育者が声を掛けなくても身の回りのことを少しずつ意識して行おうとする姿が見られた。
- 誕生会などの行事が今年度最後であることを理解し、意欲的に取り組む姿が見られた。その反面、気持ちが高揚しすぎてしまったり話を聞くまでに時間がかかってしまうことが多くあった。
- お別れ会は、屋上での開催となったがお別れ会の意味を知り、しっかりと年長児に感謝の気持ちを伝えることが出来ていた。
- 食事の際、食器上にご飯粒等が残っている子が多くいたが、集め方をしっかりと伝えたところ意識して食器を綺麗にすることが出来ていた。
ねらい
- 自分の顔に興味を持ち、似顔絵を描く経験をする。
- 友達とルールや順番を決めて遊ぶ楽しさを味わう。
- ひな祭りについて知り、興味を持つ。
- ひな祭りにちなんだゲームに参加し、ひな祭りの雰囲気や箸を使う楽しさを味わう。
- 交通ルールを意識しながら歩く。
- 固定遊具に挑戦しようとする。
- ゲームで友達と競いながら嬉しさや悔しさを味わう。
- 体を十分に動かし心地良さを感じる。
- みんなで一つの作品を作る楽しさを味わう。
- 器具や遊具を使って体をコントロールさせる。
- カスタネットの持ち方、鳴らし方を知る。
- 友達とリズムを合わせて鳴らす楽しさを味わう。
- 保育者や友達と一緒に春の探索活動を楽しむ。
- 好きな遊びを満足のいくまで楽しむ。
- 一年間使った保育室に感謝しながら掃除をする。
- 戸外に出て探索や小集団遊びを楽しむ。
- 年長児に感謝の気持ちを伝える。
- 年長児の姿を見て憧れの気持ちを持つ。
- 春の自然を見つけながら遊びを楽しむ。
月間行事
- 身体測定
- 避難訓練
- 誕生会
養護
- 友達と遊び方を考えながら遊ぶ楽しさを味わう。
- 戸外や運動遊びを通して体を動かし気持ちを発散させる。
- 身嗜みや身の回りの準備・整理を丁寧に行い気持ち良く過ごす。
- 自分の気持ちを言葉で表現して伝え、相手の気持ちにも気付く。
- お別れ会を通して年長児に対する感謝の気持ちを表現する。
- 新しいクラスでの生活の流れを知り、身の回りのことを自分でやろうとする。
- 友達や保育者に親しみ、安心できる環境の中でのびのび過ごす。
教育
- ひな祭りについて興味や関心を深める。
- 身の回りのことを率先して行おうとする。
- 簡単なゲームを通して友達と競う楽しさを味わう。
- 楽器に触れ、音の鳴らし方やリズムの合わせ方を知り楽しむ。
- 戸外で春の風を感じながら、好きな遊びを満足のいくまで楽しむ。
- 運動遊びを通して体力をつける。
- その日の出来事や印象に残ったことを言葉にして伝える。
- 一年間使った部屋に感謝の気持ちを込めながら綺麗にする。
- 静と動の活動でメリハリをつける。
- 草花や生き物に触れ、春の自然に興味関心を持つ。
- 遊びを通して友達や保育者と一緒に過ごすことを楽しむ。
環境構成
- 制作できる人数や時間を区切っておくことで、トラブルや物の紛失を未然に防ぐ。
- 運動遊びの際には、広い空間を作り十分に身体を動かすことができるようにしていく。
- はさみを使用するときには安全に進められるよう少人数で行い、使う子の分だけ机に用意するようにしていく。
- 一日の見通しを持てるよう、視覚から獲得できるようホワイトボードを使う。
- フルーツバスケットでは、イラストを用意し視覚でもわかるようにしていく。
- 運動遊びでは、バランスを崩した際にケガをしないよう青マットを多めにしいておく。
- コーナー遊びでは、好きな玩具を選択できるよう様々な玩具を用意していく。
家庭との連携
- 進級に向けて子どもたちの様子に変化が見られたり、気持ちに波が見られる頃である。先週に引き続き、面談で話すことができなかった内容や、園や家庭での様子を丁寧に伝え合い、子どもたちも保護者の方も安心できるようにする。
- 送迎時やお知らせ配信などで園生活で力を入れていること(食事のマナー等)を伝え、足並みを揃えていく。
- 気温も暖かくなってくるため、着替え袋の衣服の確認をしていただく。また、身丈に合った衣服を用意していただく。
- 進級に向けて、子どもたちが身の回りのことを自分で頑張っている姿をお迎え時やお知らせ配信で伝え、家庭でも無理なく少しずつ自分でできることを増やしてもらう。
- 体力が落ちている子が多く見受けられる為、1日の様子を家庭と共有しながら引き続き生活リズムを整えていく。
- 新年度に向けての準備物や共有事項を伝え、安心して次クラスに進級できるようにする。
- 一年間の成長をお知らせ配信で伝えたり送迎時に話したりする。また、一年間の感謝の気持ちを伝える。
- 登園時、降園時に保護者の方と様子を伝え合いながら、信頼関係を深めていく。また、環境の変化により気持ちが不安定になることも予想されるため、細かな変化を共有しながら子どもの気持ちに寄り添っていく。