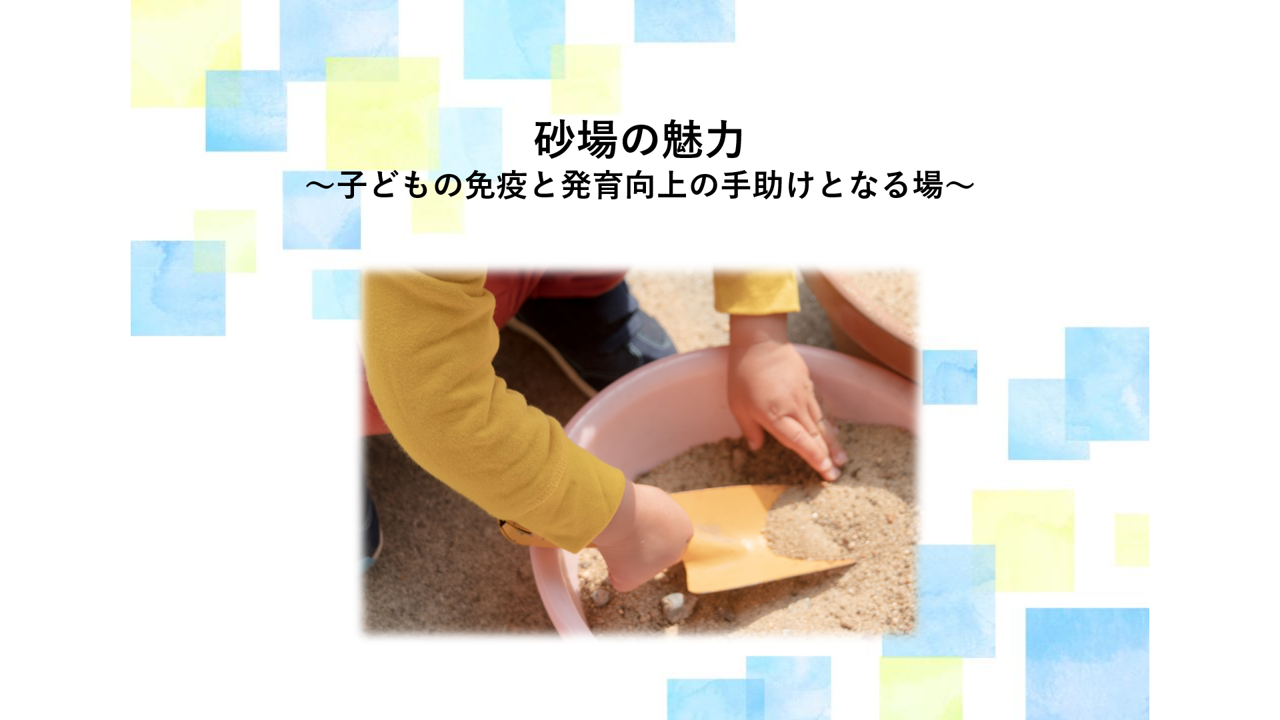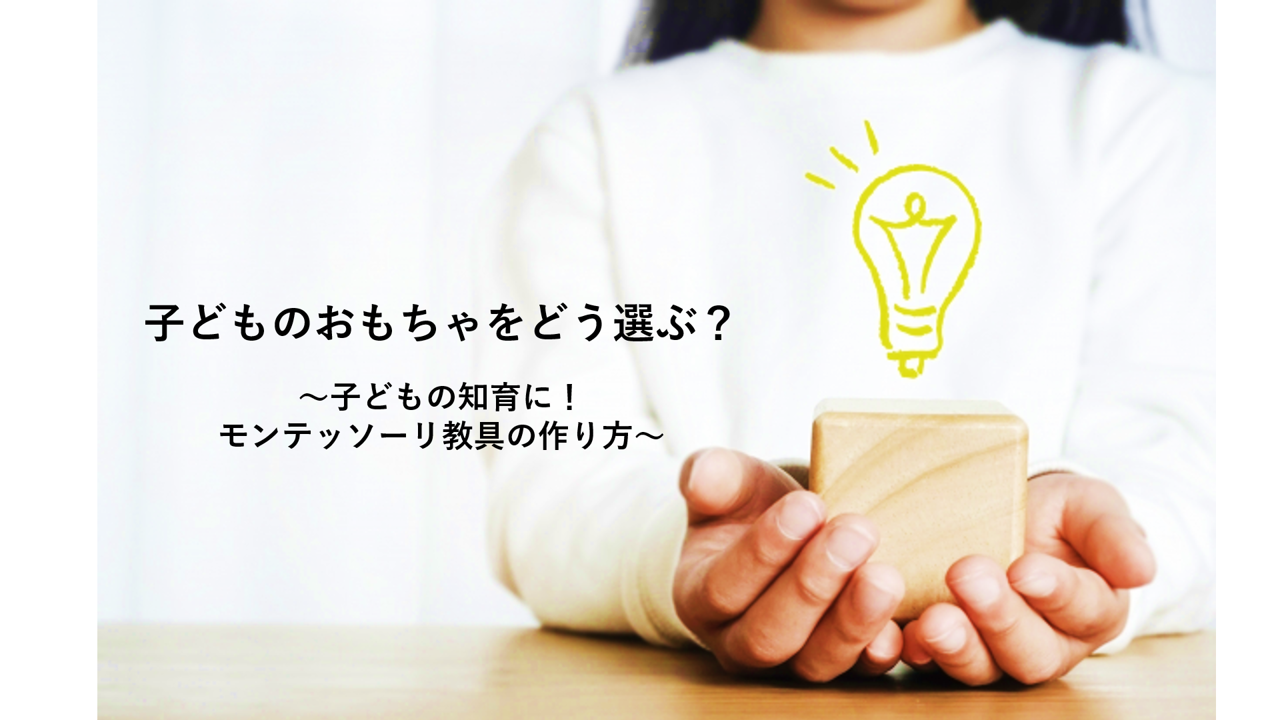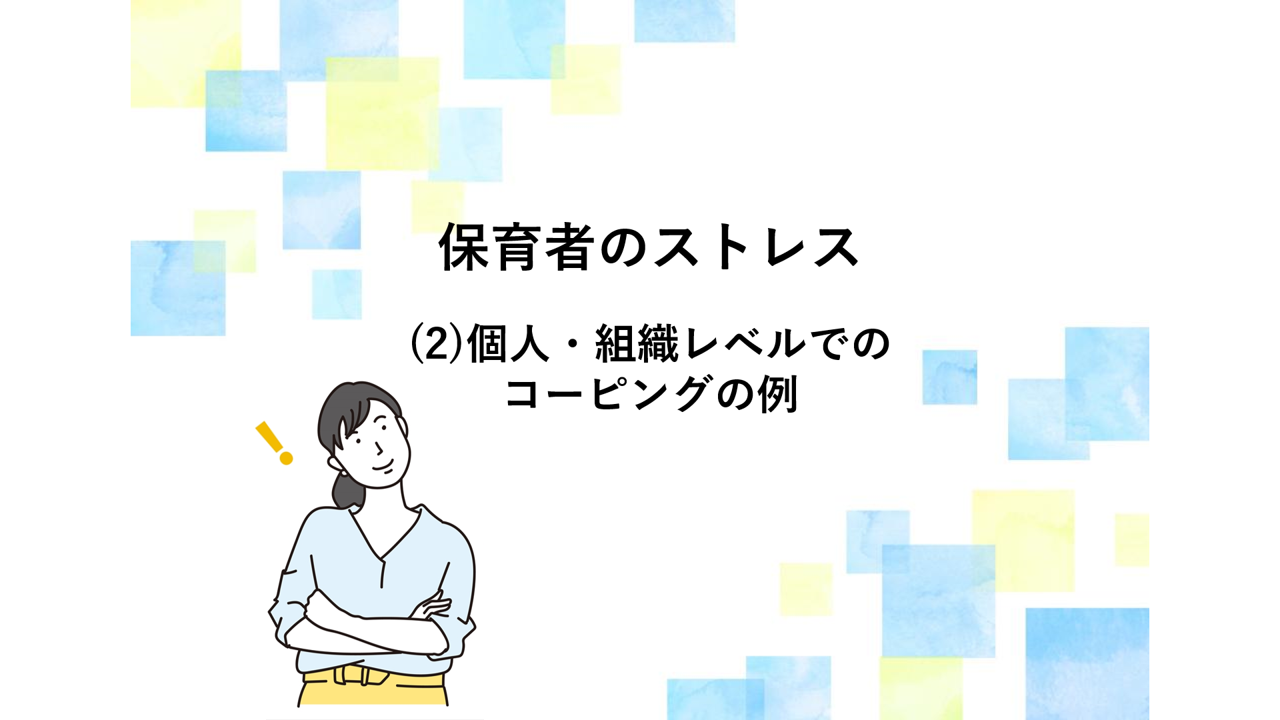▼年齢別の週案記入例は下記記事にてご紹介!
子どもの姿
- 上靴をトイレの際や、マットの上で遊ぶ際に脱いで、その後そのまま過ごしてしまう事がある。声掛けをすると気付き履こうとする姿も見られる為繰り返し知らせて意識出来るようにしていく。
- 上着を着る際、両腕を自分で入れる事が出来る子もいれば、難しい子もいる。援助をしながら着方を知らせていく。
- 自分から尿意を知らせる事が出来る子が増えてきている。遊びに集中している時はなかなか伝えられない事もある為、今後もこまめに尿意の有無を確認して自分から知らせられるようにしていく。
- 「時計の針が○になったらお片付けしようね」と伝えて、気持ちの切り替えがスムーズに行えるようになってきている。引き続き見通しをもって行動出来るように声かけをしていく。
- 食後に自分で手や口の周りを鏡で確認し、綺麗にしようとすることに慣れてきている。完全に綺麗に拭き取れていないこともあるため仕上げ確認をしていく。
ねらい
- 鼻水を拭いた後は手を洗い清潔にする。
- 作りたい物を保育者の援助を受けながら形にしてみようとする。
- 高さのある所から両足ジャンプをしてみようとする。
- 尿意を感じたら保育者に知らせトイレで排泄しようとする。
- 節分の由来や内容を知り、楽しく会に参加する。
- 手洗いの際ひじ上まで袖をまくってみようとする。
- 広場で他児と鬼ごっこやしっぽとりを楽しむ。
- 左右を確認して靴を履こうとする。
- 席から立つ時は自ら椅子をしまおうとする。
- 保育者の仲介のもと、相手の気持ちに気付く。
- 他児に自分の気持ちを言葉で伝える。
- 身の回りの始末を積極的にやってみようとする。
- 生活の中で順番を意識し、まもろうとする。
月間行事
- 身体測定
- 誕生会
- 避難訓練
- 節分会
- 食育
- 不審者訓練
養護
- 保育者の声掛けを聞き、時計を見て次の活動の支度をしようとする。
- 食後口回りが汚れていないか確認してみようとする。
- 衣服や上靴など、身に着けている物の管理をしようとする。
- 食後手口を自分で清潔にし、確認をする。
教育
- 保育者に見守られながら、荷物を鞄にしまい帰り支度をしようとする。
- 保育者と一緒に様々な物の数を数え数字に興味を持つ。
- 声掛けを聞いたり時間を意識して次の行動に移ってみようとする。
- 落ち着いて自分の気持ちを他児に言葉で伝えようとする。
- 順番を意識して並ぼうとする。
環境構成
- 植え込み裏などもゴミが落ちていないか
- 怪我の危険はないかなど、事前に確認
- 共有を行い、安全に遊べるようにする。
- トラブルを防ぐ為、間隔を空けながら並べるようにする。
- 出入口や公園の境界・トイレなどに目を配り、公園内で安全に遊べるようにする。
- 散歩では「白い線の中歩こうね」と声かけをすることで白線を意識して歩けるようにする。
- ハンドソープはそれぞれが出しやすい場所に配置しておく。
家庭との連携
- 寒さが厳しくなり体調を崩しやすくなるので、家庭と園での様子を詳しく伝え合い、変化があった時にはすぐに気づけるようにしていく。
- 個人面談が始まる為、限られた時間内で情報共有を行う。
- 面談後の自宅での様子なども詳しく聞き、家庭と園との連携を図る。
- ロッカーの中の衣服の枚数を知らせることで不足しないようにしていく。
- 上靴の持ち帰りがある為、洗濯とサイズの確認をお願いする。
- 進級に向けての取り組みを伝える事で、家庭でも期待を持てるような声掛けをして頂く。