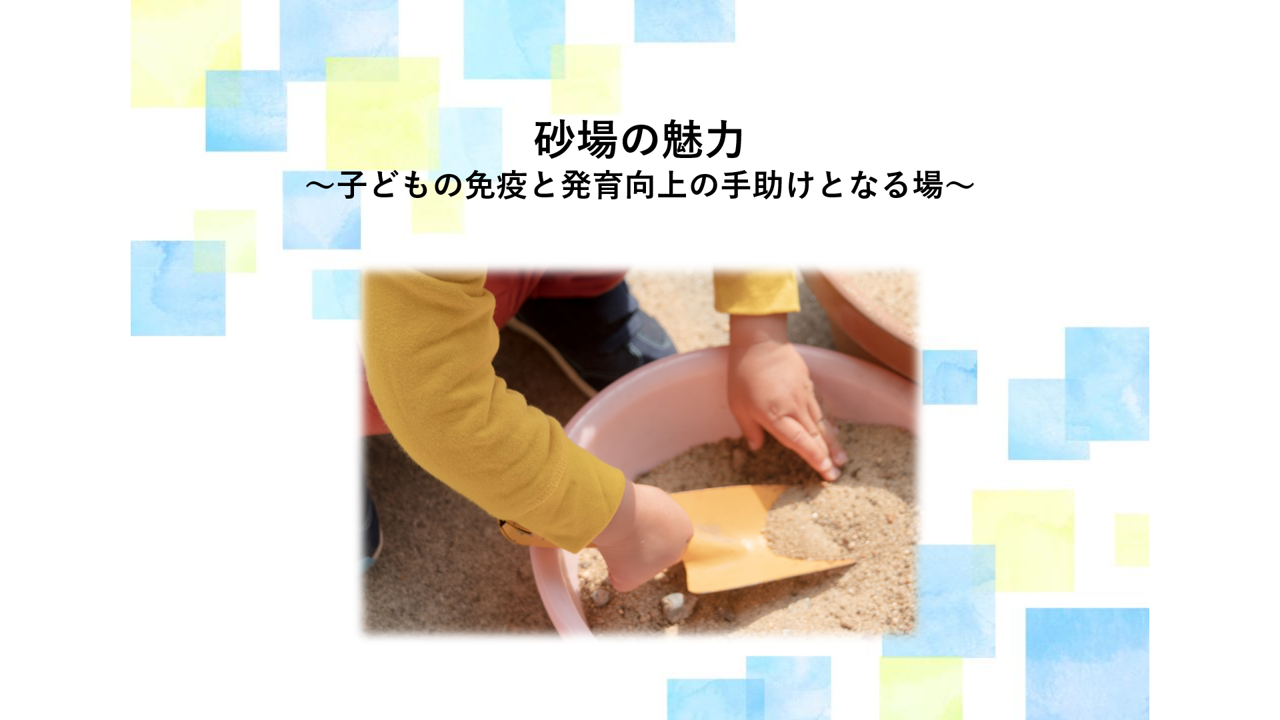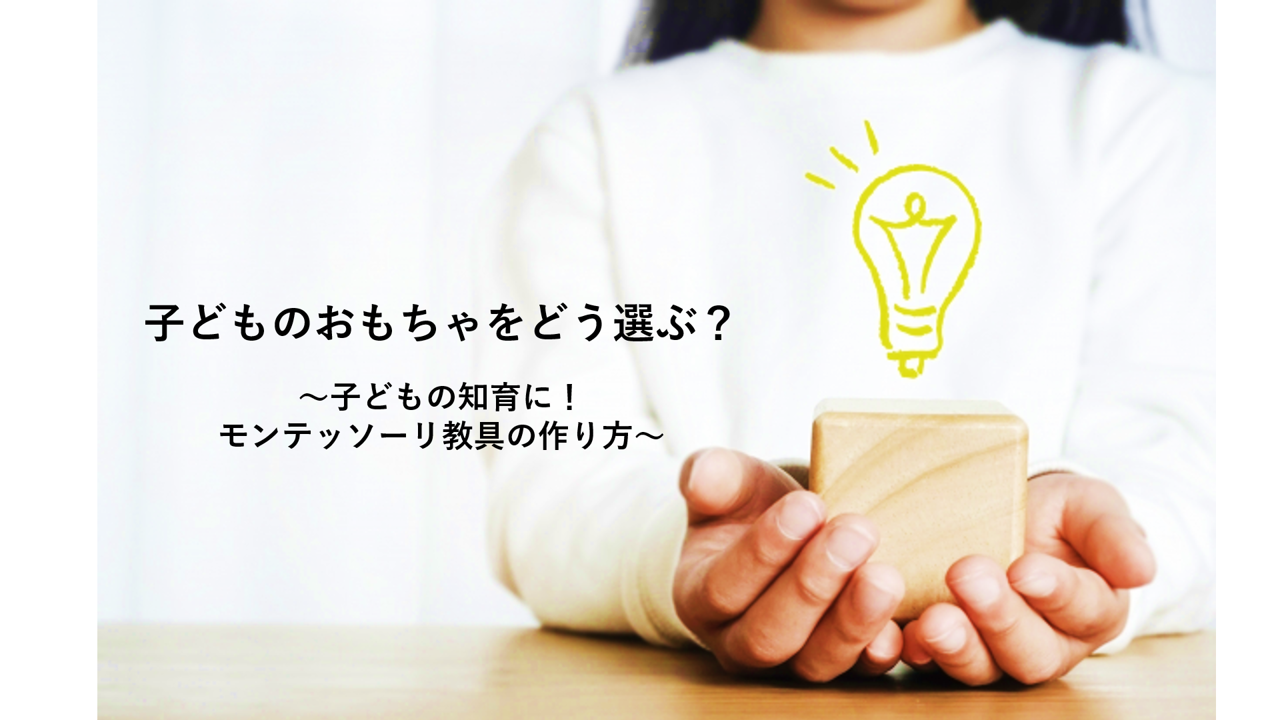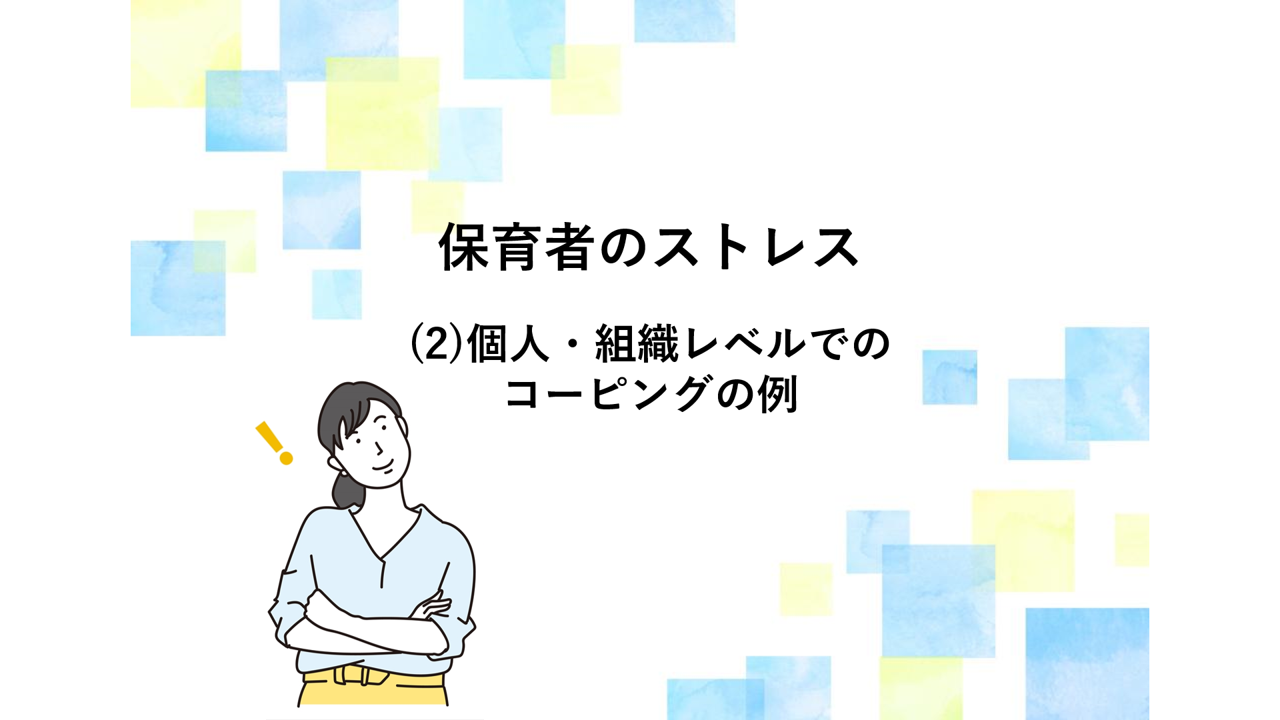ももいくナビでは、実際の保育現場で使える月案の記入例を年齢別×月別にご紹介しています。
本記事では、0歳児9月月案の記入例をご紹介します。
子どもの姿
- つかまり立ち、つたい歩き、1人歩きで活発に動いている。
- 喃語がますます盛んになり、保育者とのコミュニケーションを楽しんでいる。
ねらい
- 夏の疲れや気候の変化に留意し、一人ひとりの健康状態に合わせて生活リズムを整え、心身ともにゆったりと過ごす。
月間予定
- 避難訓練
- 身体測定
- 食育(お月見団子作り)
- 敬老の日
- 小遠足(1,2歳)
- 誕生会
- 体操あそび
養護
- 戸外遊びの後には水分補給を行い、健康的に過ごせるようにする。
- 自ら食具に触れたり、スプーンやフォークを握り口に運べるように援助する。
教育
- つたい歩きや歩行で移動し、体力をつけていく。
- 手遊びや歌などを通じ、五感を刺激して保育者の模倣をして楽しむ。
環境構成
- 室温と外気温の差を考慮し、冷房の調節をし、心地良く過ごせるようにする。
- 絵本コーナーやおままごとコーナーなど活動ごとのコーナーを作る。
家庭との連携
- 夏の疲れから体調を崩しやすいので、体調や食事、睡眠の状態を細かく伝え合う。
ももいくナビでは、実際の保育現場で使える月案の記入例を年齢別×月別にご紹介しています。
本記事では、2歳児9月月案の記入例をご紹介します。
子どもの姿
- 好きな遊びを通して、友だちとコミュニケーションを楽しむ等関わりが広がっている様子が見られる。
- 室内でのサーキットや運動遊びでは、友だちや保育者の動きを真似ようとしたり、様々なコーナーを楽しんだりしている。
- パンツへの興味が高まっている姿もあり、パンツを履きたいと伝えたり、トイレでの排泄に成功したことを保育者と一緒に喜んだりしている。
ねらい
- 外遊びに適した時期であり、様々な運動遊びを体験し、体力をつけていく。
- 室内において五感の刺激を受ける遊びを楽しむ。
月間予定
- 引き渡し訓練
- 食育
- 身体測定
- 敬老の日
- 小遠足
- 誕生会
- 体操あそび
- 十五夜会
養護
- 保育者の援助を受けながらも身の回りのことを自分で行ってみようとする意欲を受け止め、見守っていく。
教育
- 戸外遊びから戻ったら、手を洗い感染症の予防に努める。
- おいかけっこ、かくれんぼ等全身運動を行い、体力をつけていく。
環境構成
- 気温や運動量によって衣服の調節などをこまめに行なう。
- 室内備品や玩具の安全点検をし、遊びに集中できるようにする。
家庭との連携
- 残暑や夏の疲れから、体調を崩しやすくなっている為、健康状態について家庭との連絡を密にする。
- 感染症の早期発見、早期治療について伝えていく。
ももいくナビでは、実際の保育現場で使える月案の記入例を年齢別×月別にご紹介しています。
本記事では、1歳児9月月案の記入例をご紹介します。
子どもの姿
- 戸外で探索活動を積極的に行おうとしている。
- 保育者と一緒に着脱しようと挑戦し、頑張っている。
ねらい
- 着脱など、身のまわりのことを意欲的に自分でやってみようとする。
- 友達との関わりが増え自分の思いを言葉や動作で伝える。
月間予定
- 避難訓練(引渡し)
- 身体測定
- 食育(お月見団子作り)
- 小遠足
- 誕生会
- 体操あそび
養護
- 全身を使った遊びが出来るように環境を整え、工夫した遊びを提供していく。
- 楽しみながら食べ進められるような雰囲気作りをし、食べ物の美味しさを感じられるような声掛けをしていく。
教育
- 戸外から戻った際は手洗いを行い清潔を保つ。
- 言葉や体操遊びを通して他児と一緒に身体を動かして遊び楽しさを味わう。
環境構成
- 探索活動が十分にできるように安全な環境や活動の状態、子どもの相互に関わりなど十分に注意を払っていく。
- 気温や運動量によって衣服の調節などこまめに行う。
家庭との連携
ももいくナビでは、実際の保育現場で使える月案の記入例を年齢別×月別にご紹介しています。
本記事では、5歳児9月月案の記入例をご紹介します。
子どもの姿
- 夏季休暇を終えた子どもが多く家族でゆったり過ごす時間があったため、満足した状態で登園する姿が見られた。
- 年長児のみの参加のお泊まり保育では準備期間から意欲や期待感を高めて実施することができた。様々な経験を通して、挑戦しようとする意欲が見られた。
ねらい
- 自分なりに目的を持ち、いろいろな遊びに挑戦し、達成感や充実感を妹わう。
- 友達と互いに思いや考えを出し合い、力を合わせて遊びを進めようとする。
月間予定
- 避難訓練
- 園外保育
- 敬老の日
- お月見会
- お泊り保育
- 誕生曰会
- 英語教室
- 身体測定
養護
- 友だちと一緒に運動遊びやリズム遊びなどを積極的に楽しむ。
- 共通の遊びの中で、お互いの思いや考えを共有し、気持ちを認めあいながら関わりを深めていく。
- 健康で快適に過ごせるように、暑いときには自分で服を脱いで調整したり、疲れたら体を休めたりする。
教育
- 友だちと同じ目標に向かって協力しあって作り上げる楽しさを感じる。
- 人前に立つ経験を通して自信や達成感を感じ、様々なことを挑戦しようとする。
- 危機管理について子どもたちで話し合う時間をつくり、子どもたちが自分から安全に注意しながら遊べるように関わっていく。
環境構成
- 曲に合わせてダンスなどをして楽しめるように、子どもたちの好きな曲やCDなどを用意しておく。
- 運動用具を取り出しやすいように整理しておく。
- 言葉遊びの楽しさを知り、想像が広がるような遊びを取り入れる。
家庭との連携
- 暑い曰や活動量が多いため家庭との連絡を密にとり身体を休めたり、生活リズムを整え健康管理に留意しながら生活を送る。
評価・反省
- 行事の多い月となり、子ども達も積極的に参加する姿が見られた。気持ちを言葉で表現することから相手の立場にたって考えたりすることも出来ていた。運動会練習を通して諦めず最後まで行うことの大切さや自信を持って取り組めていた。
秋の発表会に向けて園児同士で話し合ったり役割分担をしたりする場面を作ってみましょう!秋の発表会の計画についてはこの本をチェック!👇