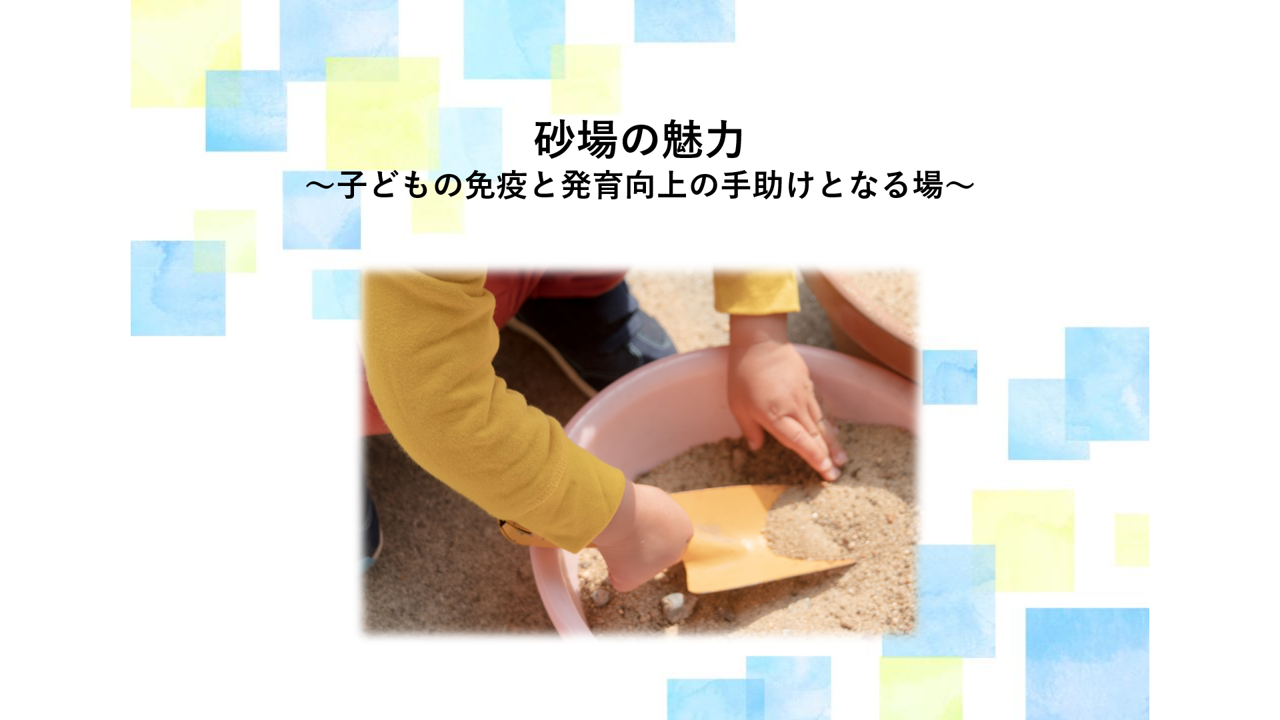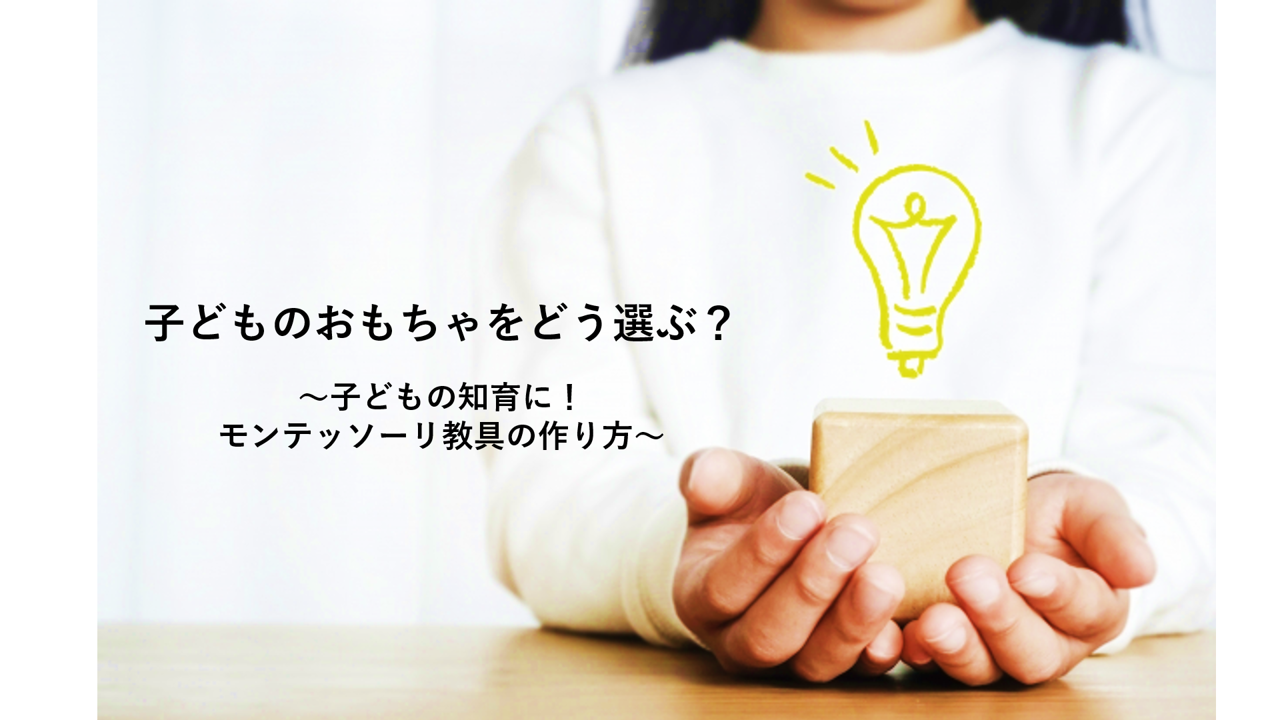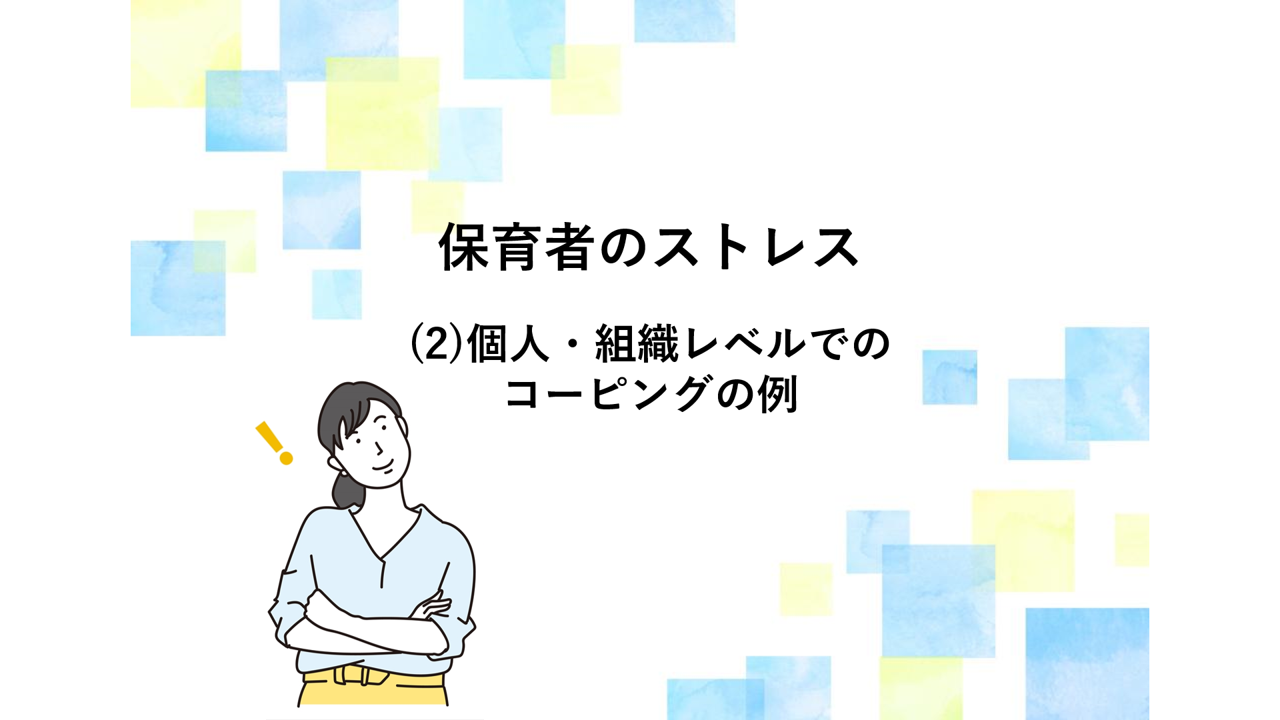▼年齢別の週案記入例は下記記事にてご紹介!
子どもの姿
- クリスマスや冬至など季節の行事について保育者が由来や意味を話すと興味を持ち話を終えた後疑問に思ったことを聞きにくる児が多かった。興味の幅が広く本や玩具を通して様々なことを伝えていきたいと感じた。
- 年中児と戸外へ2回行った。自然な流れで一緒に遊ぶことができておりより仲が深まった。また遊具を一人で登れない姿を見かけると4~5人程が協力して登る手伝いをするなど思いやりや優しい面をみることが出来た。
- 大掃除ではなぜ掃除をするのかを子どもたちと考える時間を設けた。子どもたちからは「次使う人が気持ちよく使えるようにする」「汚いから」など沢山の意見が出た。保育者はそれらも理由としてあるが、「感謝すること」を伝えた。そして今までたくさんの時間を保育室で過ごしてきた為、1年の感謝を込めて掃除をすることができるよう子どもたちに伝えた。子どもたちは積極的に掃除を行ない、きれいになった保育室を見て達成感を感じていた。
- 戸外を見てみると雪が降っており子どもたちは「雪だ、きれいだね」「触ってみたいね」等と盛り上がっていた。おやつを食べ終え、「雪見に行く?」と保育者が問いかけると「行きたい」と答えたため戸外へ出て雪遊びをした。雪合戦や雪だるまづくりなどをし雪の感触や冷たさを感じながら楽しんだ。
- みんなが作ったお店に年少児を招待することになり何を準備したらよいか、何をしたら喜んでくれるか等の話し合いをし2グループに分かれて制作を進めていた。
- 発表会へ向けて劇遊びや合奏を行なうことが多かった。劇は今まであまり取り組んでおらず子どもたちが「やりたい。」と伝えてきた際は一緒に行なう程度であったが子どもたちは台詞、歌、ダンスを良く覚えていた。また取り組んでいる際の表情は楽しそうで発表会への期待感や楽しみな気持ちが窺えた。
- 広くなった保育室を使い発表会遊びをした。台本を壁に掲示しており子どもたちは良く見ていたため、自分の台詞はほとんど言えていた。また他児の台詞も覚えていたようで忘れてしまった児に小さな声で教える姿があった。またハンドベル→合唱→合奏と順番に行なうことも初めてで保育者もとても感動した。
- 戸外では話し合いを行ない時間を区切って遊ぶことやルールを少しアレンジして遊ぶことが出来ていた。寒い日々が続いているが寒さにも負けず元気に遊んでいた。
ねらい
- お正月とはどんな由来なのかを話を真剣に聞き、会を通してお餅つきに参加したり伝承遊びに触れて楽しむ。
- 戸外へ散歩に出かけ、朝と日中の気温の差を感じながらも身体を動かして運動遊びを楽しむ。
- 年下の児と戸外へ散歩に行き、関わる事で、優しくする事や、お世話をしたり、労わる気持ちを育んでいく。
- 室内でボードゲームを行ない、ルールを守りながら遊び、子ども同士の考えや意見を大切にし折り合いをつけて遊ぶ。
- 一人ひとり納得した上で決めた公園へ行き目的の事を達成したり身体を動かす事を楽しむ。
- 室内で廃材を使って目的の物を作る途中で他児と一緒に協力したり話し合いながら目的の物を完成させていく。
- 意見を聞き合う中で他児と一緒に考え意見をまとめていく。
- 接し方や伝え方の難しさを感じながらも年少児と関わることを楽しむ。
- 年少児に喜んでもらいつつ自分も楽しめるようはりきって取り組む。
- 集中力を切らさず、自分の納得のいく作品を作る。
- ひらがなや数字、様々なプリントを行ない保育者の話を聞きながら集中してワークに取り組んでいく。
- 実際に地震や火事が起こったらどうなるのかを想像しながら避難訓練に参加をし子ども同士で声を掛け合っていく。
- 意見を伝える際に理由もつけて話す。
- 保育者に対してではなく他児に対して話すことを心がける。
- 手先を器用に使って集中して取り組む。
- 話を聞く際の目線や聞き方を自分で意識する。
- 優しさや思いやりとは何か自分なりに考えて年下児と接してみる。
月間行事
- 正月会
- 誕生会
- 身体測定
- 避難訓練
養護
- 保育者から積極的に新年の挨拶を子どもに伝えたり、お正月にちなんだ話を子どもたちとして興味を持てるようにしていく。
- 伝承遊びを正するだけではなく、それぞれ遊びにも歴史がある事を子どもに話をしていく。
- 冬の自然事象に興味や関心をもち、遊びに取り入れて楽しむことができる環境をつくっていく。
- 一人ひとりが自信を持って、発表会の練習を進めていけるようにしていく。
- 子どもたちが考えたアイデアをもとに自由に環境を作っていけるよう声掛けや援助をする。
- 戸外では一緒に遊びを楽しみながら子ども同士の遊びを発展が出来るように声を掛けていく。
- 相手の話を聞く際の正しい姿勢、頷くことや相槌をすることで相手の話しやすい環境を作ることができるということを伝えていく。
教育
- 新年の挨拶を友だちや保育者に伝え、言葉のやり取りを交わしながら年が明けたことを感じる。
- お正月会では由来や、伝承遊びなどに興味を持ち、実際に触れたりして楽しんで過ごしていく。
- 発表会に期待感を持ちながら発表会遊びに取り組む。
- 年少児との関わりを通して楽しさや一生懸命取り組んだことで喜んでもらえる嬉しさを感じる。
- 自分の気持ちに折り合いを付けながら友だちと過ごす事を楽しむ。
- 他児と一緒に遊びを楽しみながらも怪我のないように考えながら遊びを楽しむ。
- 自分なりの目標に向かって根気強く取り組み、できた満足感を味わう。
環境構成
- 伝承遊びの玩具や、餅つきに使ううす等を用意していく。
- 公園で使いたい玩具等を自分で選んで持っていけるよう環境を整えていく。
- 関わりが持てるように手を繋げるような環境を作っていく。
- 様々なルールのあるボードゲームを用意していく。
- 話し合いができるような環境を整えていく。
- 様々な種類の廃材を用意していく。
- 広いスペースで劇遊びが行えるよう机や棚を端に寄せる。
- 感染症予防の為、こまめな換気やなるべく密集しないよう時間を区切って交流をする。
- 机や棚等を子どもたちが考えた位置に配置する。
- 制作に必要な材料を保育者が準備し道具は子どもたちが準備できるよう声を掛ける。
- 避難靴や防災頭巾等取りやすく分かりやすい場所に置いてあるか確認をする。
- 全員が意見を言いやすい環境や雰囲気を作っていく。
- 制作をスムーズに行なう為、事前に材料や道具はまとめておく。
家庭との連携
- 感染症が流行るので、家庭でも手洗いうがいを徹底していくことができるようにする。また、感染症になってしまったときの対応についても説明したり、掲示したりしておく。
- 就学に向けて、子ども自身が保育園の荷物を用意したり、服装を考えていくことができるようにしていく。
- 新年の挨拶をし見通しを持って保護者の方に伝えていく。
- 発表会に向けての取り組みを伝え、準備する物への協力を依頼する。
- 年末年始で過ごしてきた生活リズムから徐々に規則正しい生活リズムにしていけるよう、連携を取っていく。また就学前の面談にて伸ばしていく所や見直していく所を伝えていく。